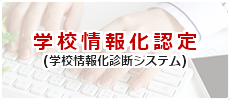スクールフォトレポート
2025/07/24
沼津市立今沢小学校
大きくて明るい画面でプレゼンしたい!

多言語な子供たちと学ぶ全ての子供の多文化共生における自己肯定感の育成をめざした教育実践
~日本特有の教科領域の学びにおける一台端末と大型画面の効果的活用~
パナソニック教育財団による助成により,75インチの大型画面を購入することができ,Umi(国際室)で学ぶ子どもの学びが変わってきました。グリーンカーテンとして育てている野菜の観察,世話を通し,収穫できた野菜を家に持ち帰り,それぞれの家庭料理をどのように作ったのか,画像にとり,家族にインタビューしたことを自主的に一台端末を活用しまとめ,プレゼンするようになりました。大型画面の分割機能も自分たちで見つけ,発表後に出身国ごとの似ている料理や違いに気付き分割画像で並べて表示し考えを発表し合う工夫がみられました。互いの発表に拍手を送り価値を認め合いルーツに対する誇りとプレゼンできた達成感から次なる意欲を高めていました。日本ならではの季節と旬に対する思いを自分のもつ複数言語で思考し言語化する過程を経て仲間と対話的に学びを深め総合的に言葉の力を高めています。新しい大型画面活用が始まり「理科が好きになってきた。」「家庭科の時に発表した。」「詩を書いてみた。」と語り,笑顔があふれるようになりました。休み時間に集まる他学年の子どもや在籍学級の友達にプレゼンしたり,使い方を教えたりする姿が日常的に見られるようになりました。また,全校児童に向けた多言語絵本の紹介CM作り等子どもの発想を生かした「ことば教育」も進めています。CMについては,映像のプロとのコラボを望む声,PanasonicのKWN(KID WITNESS NEWS)にチャレンジしてみたいという声が子どもからあがっています。
職員室の休憩スペースの衝立には,画像と説明の入った全学年の教職員の大型画面と一台端末活用事例を月替わりで載せています。職員が気軽にICT活用例を語り合える場にもなっています。
子供たちの学びを,隣接する中学校の先生方とも一緒になり研修しています。6月には小学校全クラスで公開授業をしました。授業者が事前に中学の先生を指名し公開授業におけるCLD児の抽出児の実態把握や支援に指名された中学の先生が関わり,事後研修において支援方法について互いに語り合いました。
また,7月第2週には,大阪大学の櫻井千穂准教授によるオンライン小中合同研修を実施し多文化多言語の子ども(CLD児)を理解し支援するための理論を対話的に学びました。前述の大型画面はZoomでつなぎ,既存のやや小ぶりの画面に研修参加者の意見やグループ発表を個々の一台端末から瞬時に集めAIテキストマイニングしたものを映しリアルタイムで情報共有し議論を深めました。
7月第3週には,JICAオンライン出前授業で海外(フィジー)とつなぎ,CLD児だけでなく学年全体(小6)で合同Umiキャリア学習を実施する予定です。
9月には,Umi防災・キャリア学習を「海」と関連付けながら京都大学舞鶴水産実験所長の益田玲爾教授と対面で大型画面を活用しながらダイナミックに語り合う授業を予定しています。
今後も様々な環境下で育ってきた子どもを包摂し,子どもが伝えたい思いに寄り添い,子どもがデジタル学習基盤を使い自分の考えを主体的に伝える力を育てるとともに,個別最適な深い学び,互いの価値を認め高め合う授業づくりを学校全体で進めていきます。そのために子どもや教職員,保護者の振り返りをもとに現状分析し,研究を深化させていく予定です。
~日本特有の教科領域の学びにおける一台端末と大型画面の効果的活用~
パナソニック教育財団による助成により,75インチの大型画面を購入することができ,Umi(国際室)で学ぶ子どもの学びが変わってきました。グリーンカーテンとして育てている野菜の観察,世話を通し,収穫できた野菜を家に持ち帰り,それぞれの家庭料理をどのように作ったのか,画像にとり,家族にインタビューしたことを自主的に一台端末を活用しまとめ,プレゼンするようになりました。大型画面の分割機能も自分たちで見つけ,発表後に出身国ごとの似ている料理や違いに気付き分割画像で並べて表示し考えを発表し合う工夫がみられました。互いの発表に拍手を送り価値を認め合いルーツに対する誇りとプレゼンできた達成感から次なる意欲を高めていました。日本ならではの季節と旬に対する思いを自分のもつ複数言語で思考し言語化する過程を経て仲間と対話的に学びを深め総合的に言葉の力を高めています。新しい大型画面活用が始まり「理科が好きになってきた。」「家庭科の時に発表した。」「詩を書いてみた。」と語り,笑顔があふれるようになりました。休み時間に集まる他学年の子どもや在籍学級の友達にプレゼンしたり,使い方を教えたりする姿が日常的に見られるようになりました。また,全校児童に向けた多言語絵本の紹介CM作り等子どもの発想を生かした「ことば教育」も進めています。CMについては,映像のプロとのコラボを望む声,PanasonicのKWN(KID WITNESS NEWS)にチャレンジしてみたいという声が子どもからあがっています。
職員室の休憩スペースの衝立には,画像と説明の入った全学年の教職員の大型画面と一台端末活用事例を月替わりで載せています。職員が気軽にICT活用例を語り合える場にもなっています。
子供たちの学びを,隣接する中学校の先生方とも一緒になり研修しています。6月には小学校全クラスで公開授業をしました。授業者が事前に中学の先生を指名し公開授業におけるCLD児の抽出児の実態把握や支援に指名された中学の先生が関わり,事後研修において支援方法について互いに語り合いました。
また,7月第2週には,大阪大学の櫻井千穂准教授によるオンライン小中合同研修を実施し多文化多言語の子ども(CLD児)を理解し支援するための理論を対話的に学びました。前述の大型画面はZoomでつなぎ,既存のやや小ぶりの画面に研修参加者の意見やグループ発表を個々の一台端末から瞬時に集めAIテキストマイニングしたものを映しリアルタイムで情報共有し議論を深めました。
7月第3週には,JICAオンライン出前授業で海外(フィジー)とつなぎ,CLD児だけでなく学年全体(小6)で合同Umiキャリア学習を実施する予定です。
9月には,Umi防災・キャリア学習を「海」と関連付けながら京都大学舞鶴水産実験所長の益田玲爾教授と対面で大型画面を活用しながらダイナミックに語り合う授業を予定しています。
今後も様々な環境下で育ってきた子どもを包摂し,子どもが伝えたい思いに寄り添い,子どもがデジタル学習基盤を使い自分の考えを主体的に伝える力を育てるとともに,個別最適な深い学び,互いの価値を認め高め合う授業づくりを学校全体で進めていきます。そのために子どもや教職員,保護者の振り返りをもとに現状分析し,研究を深化させていく予定です。
| 学校名 | 沼津市立今沢小学校 |
|---|---|
| 研究課題 | 多言語な子供たちと学ぶ全ての子供の多文化共生における自己肯定感の育成をめざした教育実践 ~日本特有の教科領域の学びにおける一台端末と大型画面の効果的活用~ |
| 都道府県 | 静岡県 |
| 学校ホームページ | https://swa.numazu-szo.ed.jp/numazu022 |