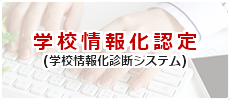2025年5月30日、2025年度(第51回)実践研究助成 助成金贈呈式・スタートアップセミナーを開催しました。会場には助成先や専門委員の先生方、ご来賓の方々約120名にお集まりいただきました。
2025年度(第51回)助成金贈呈式・スタートアップセミナー
(東京都墨田区)


第1部の助成金贈呈式では主催者挨拶、文部科学省様からのご祝辞とご講演、助成先代表の抱負、選考委員長からの励ましの言葉に続いて、前年度の「研究成果報告書」表彰校3校による事例発表とパネルディスカッションが行われました。
第2部のスタートアップセミナーでは、助成先の皆様と専門委員の先生方が20のグループに分かれて、実践研究の内容について協議するグループディスカッションを行いました。
第3部の交流会では、助成先の皆様や専門委員の先生方がこの日の発表を振り返り、情報を交換し、交流を深めました。「GIGAスクール構想」によって整備されたICT環境を活かし、よりよい実践事例をどう積み上げていくのか、生成AIの利活用をはじめとする多くの事例をもとに考えを深め、新たな気づきを得る1日となりました。
第1部 助成金贈呈式
主催者挨拶

GIGAスクール構想が日本の学力向上に寄与
生成AIに創造力や企画力、思考力をプラス
パナソニック教育財団 理事長 小野 元之
2023年に50周年を迎えたパナソニック教育財団は、これまでにのべ3582件の助成を行ってきました。全国の初等中等教育の学校数が約3万5000校なので、約10%に助成金を差し上げたことになります。2025年度は特別研究指定校5件、一般助成校226件の応募があり、前年と比べて10%ほど増え、その中から特別研究指定校2件、一般助成校68件の助成が決まりました。
学習到達度調査PISA2022で、日本はOECDの中でも世界トップレベルを獲得し、IEAが実施したTIMSS2023でも同様の結果を残し、GIGAスクール構想が学力の向上に役立っていることが証明されました。生成AIが私どもの生活や仕事に与える影響が懸念されていますが、AIによって平均的な見解を知り、60~70点を取ることはできても、創造力や企画力、思考力によって、それを90~100点にしていくことが必要なのだと思います。
一人一台端末の環境は整いましたが、子どもたちはまだゲームやSNS、気に入った情報を得ることが中心で、学校の教育現場だけでなく、家に持ち帰って学習に活用するところまでは使いきれていません。文部科学省が推進する教育DXの流れの中で、私ども財団の助成金を活用していただき、GIGAスクール構想の成果を最大限発揮できるよう、学校現場をサポートし、日本のICT教育の向上に、これからも努力していきたいと思っております。
文部科学大臣 あべ 俊子 様よりご祝辞

教育DXの探究と横展開により
質的向上と持続可能な教育の実現へ
文部科学省 初等中等教育局
学校情報基盤・教材課長
寺島 史朗 氏(代読)
このたび、助成を受けられることとなった学校及び研究グループの皆様、誠におめでとうございます。現在、わが国において、ICTの進化やネットワーク化により経済や社会の在り方、産業構造が急速に変化する大変革期Society5.0が到来しています。こうした中、教育においてもICTを最大限に活用し、未来社会を担う子どもたちが多様な課題を主体的に解決する力を育む環境づくりが、かつてないほど重要になっています。文部科学省は教育DXの推進を通じて、誰一人取り残すことなく、すべての子どもたちの可能性を最大限に引き出す新しい学びの実現を目指しております。
GIGAスクール構想の推進においては、先進事例が数多く創出される一方で、自治体間・学校間の格差も出てきており、令和7年度も引き続き、効果的な実践事例の創出・横展開と共に伴走支援を進めているところです。本日お集まりの皆様には、教育DXのさらなる可能性を探究すると共に、それぞれの地域や学校、教育関係機関に積極的に成果を発信していただきたいと思っております。このような取り組みの広がりが、全国規模でのICT活用の質的向上と持続可能な教育の実現につながると確信しております。文部科学省も引き続き、すべての子どもたちの可能性を最大限に伸ばす個別最適な学びと協働的な学びの一体的な実現に向け、ハード・ソフトの両面から、GIGAスクール構想の推進に取り組んでまいります。財団のますますのご発展と、助成校及び助成グループの皆様の取り組みが実り多きものとなりますことを祈念いたします。
ご講演

GIGAスクール構想の推進について
文部科学省 初等中等教育局
学校情報基盤・教材課長
寺島 史朗 氏
これから実践研究に取り組む助成先の皆様に、今、学習指導要領の改訂に向けて、どんな議論がなされ、今後どのような方向に進んでいくのか、文部科学省の資料を参照しながら、ポイントをご紹介いただきました。さらに、GIGAスクール構想の現状や効果、課題についてご発表いただき、最後に、生成AIの利活用や校務DXを研究テーマとした助成先の皆様が参照できるような資料も、ご提示いただきました。
1.学習指導要領改訂の議論(情報活用能力の抜本的向上)
今、次期学習指導要領改訂の議論が行われていますが、中でも情報活用能力の抜本的向上が大きなテーマになっています。文部科学省の問題意識は中央教育審議会への諮問文に凝縮されています。まず顕在化している課題は、デジタル学習基盤の効果的な活用は緒に就いたばかりで、デジタル人材育成の強化が喫緊の課題であり、デジタルかリアルかの二項対立に陥らず、バランス感覚をもって積極的に活用する必要があるということです。審議事項としては、情報活用能力の抜本的向上を図る方策と質の高い探究的な学びの在り方、現状と課題、海外との比較を踏まえた上での今後の具体的な充実の在り方、生成AI等の先端技術等に関わる教育内容の充実のほか、情報モラルやメディアリテラシーの育成強化について検討することを求めています。
情報活用能力の抜本的向上の課題としては、情報技術の活用において地域や学校による差が大きいこと、メディアリテラシーや負の側面への対応について学校間の差があること、コンピュータに関する科学的な理解が十分ではないことが挙げられます。そこで、小学校では、総合的な学習の時間の一部を、情報活用能力を身につける時間として位置づけること、中学校では、技術家庭科を見直して新・技術分野(仮称)を設け、その力を総合的な学習の時間にも活かすこと、高等学校では、情報科で身につける情報活用能力や探究の過程を総合的な探究の時間にも活かすことを検討しています。デジタル学習基盤は「課題の設定、情報の収集、整理・分析、まとめ・表現」という探究のプロセスにおいても、大きな価値をもっていると考えられています。
<初等中等教育における教育課程の基準等の在り方について(諮問):文部科学省>
2.GIGAスクール構想について
GIGAスクール構想は令和元年度に、一人一台端末と高速大容量の通信ネットワークを一体的に整備し、子どもたちの資質・能力を高めるためにスタートしました。個別最適な学びと協働的な学びを実現するには、学校教育の基盤的なツールとしてICTは必要不可欠であると位置づけ、わずか1、2年で、全国の小中高合わせて1200万台の端末が整備され、学力調査や学びの保障にも効果が出ています。一方で、地域・学校間の差やネットワーク環境、校務DXの推進が課題となっています。
令和6年度の全国学力・学習状況調査によれば、主体的・対話的で深い学びの課題解決に取り組む学習活動でICTを活用している学校グループほど、各教科の正答率が高いことがわかりました。しかし小・中学校では、主体的・対話的で深い学びの場面でのICT活用は不十分であることもわかってきました。そこで私どもは令和5年度から、指定校に、さまざまな実践事例を出していただくリーディングDXスクール事業を始めました。今年は特に「GIGA×主体的・対話的で深い学び」や「GIGA×教師の指導性」に取り組みたいと考え、これに先駆けて昨年度末から学習会を始めました。その内容はアーカイブでご覧いただけます。デジタル学習基盤の活用によって時間を効率化でき、生み出した時間を探究のプロセスに回すことで、質を高めることが可能になるといった研究結果も示唆されています。
<リーディングDXスクール実践事例集(令和5年度) – YouTube>
<【特別講座】【テーマ】これからのGIGA!!!教科の学びをどう深める!?>
<【リーディングDXスクール事業】これからのGIGA!デジタル学習基盤をどう生かす!?教師の指導、どう変える?~クラウドで可視化される学習状況の把握、速やかな指導・支援を考える~ (R7.3.10)>
3.生成AIの利活用について
文部科学省は昨年12月に、「生成AIの利活用に関するガイドライン(Ver.2.0)」を公表しました。この中で、基本的な考え方の一つ目は、人間中心の利活用であること。最後は人間が判断して、責任をもつことが大事です。二つ目が、ファクトチェックなどを含めた、情報活用能力をしっかり育成することです。そして、校務や学習で利活用する時に押さえておくべきポイント、利活用する際のチェックリスト、パイロット校での先進的な取り組み事例、研修教材や研修動画などのリンク集も掲載していますので、ぜひご活用ください。
<生成AIの利用について:文部科学省>
※文部科学省ホームページに掲載されている実践動画や研修動画、資料はこちらをクリックください。
【文部科学省ホームページの参考サイト】
ご講演の中で紹介されました実践の参考になる様々な動画や資料が掲載されていますので、是非、ご覧ください。
各項目をクリックすると、文部科学省ホームページのサイトに移動します。
 【動画】GIGAスクール構想 1人1台端末の活用1人1台端末で学校が変わる!
【動画】GIGAスクール構想 1人1台端末の活用1人1台端末で学校が変わる! 【動画】オンライン研修会(学校DX戦略アドバイザー事業ポータルサイトより)
【動画】オンライン研修会(学校DX戦略アドバイザー事業ポータルサイトより) 初等中等教育段階における生成AIの利用に関する暫定的なガイドライン
初等中等教育段階における生成AIの利用に関する暫定的なガイドライン StuDX Style
StuDX Style 学校DX戦略アドバイザー事業ポータルサイト
学校DX戦略アドバイザー事業ポータルサイト
奨励状授与・助成先代表抱負


本校は海と山に囲まれた自然豊かな環境にある、全校生徒数88名の小規模校です。
1小1中の学校ということもあり、幼少期から同じ集団で過ごしているためか子どもたちはなかなか自分の殻を破ることができていない様子があります。
そこで、未来を主体的に切り拓く「学び手」としての力を育成することを目指し研究を進めてきました。
昨年度も助成をいただいたおかげで、ICT環境の整った「探究ラボ教室」を設置することができ、教室を飛び出した学びが展開できるようになりました。
今年度は、ICTを活用した授業改善に取り組みながら、子どもたちの学びを支える研究をさらに進めていきたいと考えております。
今後ともご指導・ご助言のほど、どうぞよろしくお願いいたします。
選考委員長からの励ましのお言葉

すでに決まっている学校の予算と違って、パナソニック教育財団の助成金は自由に使えるところが大変ありがたく、私も昔、この研究助成金をいただいたことを今でも感謝しています。昨年、ISTEというアメリカの教育工学の学会にオンラインで参加しました。
その中に、道具が広がっていく要因を分析した興味深い研究がありました。1つは便利さを実感できること、2つ目が簡単であること、そして3つ目が、社会的に認知されていることでした。かつては、パソコンで勉強していても、遊んでいるのではないかと、お母さんから怒られたはずです。ところが今は文部科学省を始め、教育委員会も、ICTを学習に使うことを社会的に認知しています。かつては教育学や工学の専門家からも認められなかった教育工学も、世の中にとって必要だと、今は社会的に認知されています。
今のGIGAスクール構想における子どもたちの在り方も、おそらく同じだと思います。こんな教育を受けていると胸を張って言える世の中になれば、こんなにうれしいことはありません。先ほどのご講演にもありましたように、ICTが単なる道具から学習の基盤になってきたということで、財団としては、これからもますます、この分野における貢献を続けていきたいと思っています。
前年度一般助成の「研究成果報告書」表彰校発表
2024年度(第50回)一般助成の「研究成果報告書」の表彰校はこちら
表彰校による事例紹介とパネルディスカッション
<コーディネーター>
長崎大学 准教授 瀬戸崎 典夫 先生
島根大学 特任准教授 大﨑 理乃 先生
<発表校>
横浜市立旭小学校 益子 照正 先生
新潟市立小新中学校 小林 智 先生
兵庫県立氷上特別支援学校 黒田 一之 先生
最初にコーディネーターの瀬戸崎先生より「研究成果報告書」の5つの評価観点(詳細はこちら 8ページ目参照)についてお話いただき、表彰校3校の先生方に事例をご紹介いただきました。

本校はGPSテクノロジーを導入して、新しい体育科学習を創造し、初等教育に導入したいとの思いで研究を進めました。目指すところは、あくまでも児童の成長です。実施種目は40m走とタグ鬼ごっこ。慶應大学大学院と慶應キッズパフォーマンスアカデミーというスポーツクラブの協力を得て、40m走では計測タイム・最高速度・最大加速度、タグ鬼ごっこでは総運動距離・時速15m以上で動いた高強度運動距離・高強度運動比率を計測しました。
活動前の意識調査では「運動が嫌い」「やや嫌い」が18.2%。この群の子どもたちが、どう変わるかを見ていきました。計測は2カ月おきに3回で、あるお子さんは、初めはあまり競技に関わっていない様相でしたが、自分の動画を解析する学習を採り入れ、速く走れる指導を受けた結果、最後まで走り抜けるようになり、参加の仕方が変わってきました。全体を見ても、タグ鬼ごっこのタイムにはさほど変化はありませんでしたが、高強度移動距離や高強度比率が上がり、持っている力を発揮できるようになりました。実施後の意識調査からは、「自分の動画を見ながら分析したこと」や「計測データから自分の走りを知れたこと」が有効だったことがわかりました。データ活用が児童同士の学び合いにつながった一方で、教師がデータを解析できないことや有効性の検証が課題です。

本校ではSociety5.0を見据え、3年間の総合的な学習の時間を貫くテーマとして、ロボットやテクノロジーを設定し、未来社会で生き抜く力を育む探究活動を行ってきました。しかし、一人一台端末の普及と共に、教員による評価や助言が追いつかなくなり、生成AIの活用方法と教育的効果を検証することにしました。具体的には、中学3年生に夏休みの課題として、生成AIを活用してレポートを書いてきてもらったり、学級活動での家庭学習の振り返り支援にAIを活用したりしました。そして3年生の後期には、未来防災小説の共同制作にも取り組み、イラストの生成や原稿の校正・アドバイスに生成AIを活用しました。
生徒の学びに向かう力の変化を読み取るために行った成長力アンケートでは、「経験していないことでも大切だと思えることには挑戦する」「失敗に学んで成長する」といった項目が伸び、家庭学習力アンケートでは「夢をもって学習する」「わからないことは調べる」「目標を決めて学習する」といった項目が伸びました。今年度は各教科や校務にも活用を広げていきたいと考えていて、生成AIへの依存防止に配慮しつつ、学力向上に有効な活用事例を創出することが今後の課題です。

本校の研究では、知的障害特別支援学校で生成AI対話システムを開発・導入し、授業準備と振り返りでAIと対話することによって、授業のPDCAサイクルを促進し、その子に合わせた授業づくりを目指すことにしました。まずは、生成AIガイドラインの内容について全校の先生に研修を行い、AIから先生に、生徒の発達年齢や好きなこと、得意なこと、身につけさせたい力を質問します。先生が答えると、AIが5つのアイデアを提案。そこから、生徒に合ったものを先生が選びました。そうすると、指導の留意点の叩き台が出てくるので、さらにAIとの対話を重ね、その子に合わせた授業づくりをしていきました。
1カ月、10人の先生に使っていただいたところ、その生徒が好きな車の計算問題を出すなど、その子の好きなものを大事にする授業の提案が出てきました。また、振り返り支援AIとの対話では、授業で対話が成立しにくいことに課題を感じていた先生がKJ法を提案され、自分にはない発想を得ました。研究の成果としては「新しい視点や発想を得た」「教材作成の時間短縮につながった」といった点、課題としては研究参加者が少なかったことと、子どもから見て授業がよかったか検証が不十分な点が挙げられます。今回の研究のプロンプトを公開しながら、フィードバックを得て、今後の研究を加速していきたいと思います。
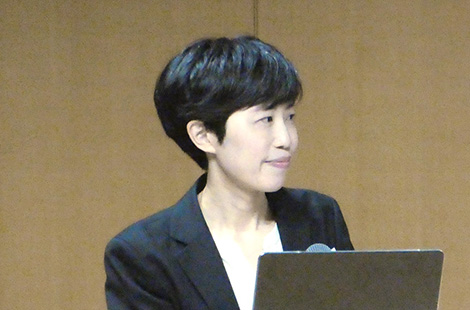
島根大学 特任准教授 大﨑 理乃 先生
●質疑応答
大﨑 先生「実践研究を学校全体での取り組みにすることや、地域や保護者、共同研究者と協働的に取り組む上での工夫や苦労について教えてください」
小林 先生「私たちは子どもたちが1年生の時から、テクノロジーやロボットを、総合的な学習の時間を貫くテーマとして設定し、未来の防災や福祉、農業、職業などについて考えてきたので、生成AIを導入することに、先生たちからも保護者からもあまり抵抗がありませんでした。夏休みの課題においても無理強いはせず、AIを使いたい人は活用し、慎重な考えの人は慎重に使いながら、レポートを書くようにしました」
大﨑 先生「実践研究を進める上で正直困ったなと思ったことや、困ったことに直面した時に、どのように対応したかを教えてください」
益子 先生「まずは、一緒に取り組んでくれる先生方を徐々に増やしていきました。あとは、子どもたちの自己成長という目指すところさえはっきりさせていれば、物理的・技術的な問題をクリアするために、活動内容はあとから調整できると気づきました。今年度のテーマは初等教育に広く浸透させるためのノウハウを明らかにすることですが、パーツがうまくいかなくても、テーマを見失わなければ、再構築は可能だと思っています」
黒田 先生「1年前だったので、AIの回答精度が低くて、先生方の課題解決につながらないのが悩みでした。そこで自分自身がAIに詳しくなって、ちゃんとしたプロンプトを書けるようになるために、民間のセミナーに参加したり、AIについて発信しているYouTubeを見たり、財団の助成金で書籍を買ったりして勉強しました。AIを導入しても活用率が上がらないのも悩みで、先生方に寄り添った伴走支援が重要だと感じました」
総括

まずは課題を明確にし、実践研究を通じて何を達成したいのか、児童生徒、教員のどのような能力を高めたいのかを明らかにすることが重要です。そこが描けていれば、計画通りにいかなくても、いろいろなやり方を工夫して、柔軟に使える財団の助成金を活かしながら、課題解決に向けた研究計画の改善と着実な遂行を実現できるのではないかと思います。今日はお三方とも、とても楽しそうにお話しされていました。皆さんも取り組まれる中で、周囲がわかってくれないとか、大変なこともあるかもしれませんが、やはり先生方自身が楽しんで、子どもたちの役に立っているところを小さなことでもいいので見つけながら、ポジティブに進めていかれるといいと思います。これまでの実践研究を参考にしながら、それぞれの学校や先生方の特徴を活かした研究を発展させていってください。
パナソニックの学校向け支援プログラムの紹介

先生方のサポートも充実した4つのプログラム
パナソニック オペレーショナルエクセレンス株式会社
企業市民活動推進部
多田 直之
私どもパナソニックは社会課題の解決に向けて、貧困の解消、環境活動、人材育成(学び支援)という3つを重点テーマとし、企業市民活動に取り組んでいます。今日は、皆様に直接関係のある学び支援のプログラムを3つ、ご紹介したいと思います。
「キッド・ウィットネス・ニュース」は小・中・高の児童・生徒に映像制作を通して、創造性やコミュニケーション能力、チームワークを育んでもらうプログラムです。世界各国の優秀賞をもらった代表校とオンラインで国際交流できる「グローバルサミット」も開催しています。また「パナソニックキッズスクール」では、1900年代の世界の暮らしを学ぶ「タイムスリップ大作戦」など、子どもたちがウェブサイト上で自ら学べる16のコンテンツをご用意しています。「私の行き方発見プログラム」は中学生が対象で、キャリア教育を目的に、実践形式で学べる6種類の教材をご用意しています。さらに、活用のヒント集やオンラインセミナー、メールマガジン、電話で、先生方のサポートもしております。
そして、今年始まったのが「みんなで“AKARI”アクション」の学校向け特別企画です。パナソニックは無電化地域にソーラーランタンを届ける活動を続けてきましたが、今回は無電化地域の子どもたちにクリスマスイルミネーションを送るために、学校でリサイクル募金として本やCDを集め、寄付をしていただきます。さらに、電気のない暮らしについて学んだ上で、現地に手紙を送って、現地からも手紙を受け取ることができます。ホームページをご覧の上、ぜひご検討ください。
第2部 スタートアップセミナー
グループディスカッション
第2部では、特別研究指定校、一般助成校が20のグループに分かれて、グループディスカッションを行いました。冒頭で、助成校の先生方が研究概要を発表。各グループには専門委員の先生方にも加わっていただき、実践研究の内容をブラッシュアップするために、意見を出し合い、情報を共有し、今後の活動方針について話し合いました。その中から、AIや仮想空間などをテーマに意見交換した、瀬戸崎 典夫 先生と三井 一希 先生のグループの様子をご紹介します。

AIボイスレコーダーを活用し、質の高い対話を目指す
西条市立神拝小学校
山下 楓馬 先生
金子 広樹 先生
本校では、トラブルが起こった時に、行動の奥深くにある相手のニーズを想像できるようにするために、昨年度から全クラスで、学級活動の中に対話の時間を採り入れました。さらに、対話的な風土を学校全体に醸成していくために、他の教科でも、取り組んでみたい先生が授業にニーズの探究を採り入れ、対話の場面が増えたことで、昨年度の児童間トラブルは減りました。
一方で、対話の反省を次の対話に活かすことができていないのではないかという課題があり、助成金でAIボイスレコーダーPLAUD NOTEを購入。録音・文字起こし・要約・マインドマップをデータ化し、対話の中身を先生も把握して、フィードバックしていきました。さらに、教育支援クラウド「スクールタクト」の振り返りAI分析を活用し、振り返りの文章が事実・感想・考察・結論のどれに当たるのかを分析。観点を意識することで表現力を向上させ、質の高い対話と自己表現力の育成につなげていきたいと考えています。
●他校の先生との質疑応答
Q「振り返りをすることが、どのように質の高い対話につながるのでしょうか?」
山下 先生「振り返りとして、自分で入力した文章をAIが分析してくれるので、そこで語彙を増やしながら、話し言葉に置き換えていけたらと思っています」
●長崎大学 瀬戸崎 典夫 先生のコメント
自分はこういうつもりで言ったのに、AIに分析させたら違っていたという、自分の思いと客観のギャップに気づいて、違う視点をもつようにするというのも面白いかもしれません。質の高い対話とは何かというところも子どもたちと一緒に考えながら、ルーブリックをつくり、どこまでできたか、段階を追って評価していくと、子どもたちが目標達成に向けて頑張れるようになると思います。
●山梨大学 三井 一希 先生のコメント
AIボイスレコーダーで作成した逐語録や要約を見て、グループごとに振り返りをする時に、プロンプトを工夫して、対話の中で、どのような語が多かったか、他者を肯定するような言葉はあったか、子どもたちに書いてもらうといいと思います。その際に、先生方が何を目指していて、何のために質の高い対話が必要なのかを常に確認しつつ、振り返るサイクルを回していけば、質の高い対話に近づいていくのではないでしょうか。

メタバースを活用した交流で「心理的距離感」を軽減
大阪市立今里小学校 斉田 俊平 先生
本校は全校児童150名、全学年単学級で、関係性が固定化されていて、多様な意見に触れるために、2年前、財団の助成を活用し、Zoomを使って、離島の小学校と遠隔交流をしました。しかし児童に聞き取りをすると、恥ずかしさや緊張など、心理面でのハードルがあり、今回は、NTTスマートコネクト社のメタバースを使って交流することにしました。仮想空間では、それぞれの部屋で会話したり、ホワイトボードを使ってプレゼンをしたり、リアクションボタンで挙手して発言したりすることができます。
昨年は実証的に6年生が、開発途上国で支援活動をしているJICAの方々に話を聞き、その国の課題を考え、課題解決的な探求学習をして発表しました。距離を感じることなく、積極的に会話できたという肯定的な回答が多い一方で、課題も見えました。翻訳機能を利用して、海外との交流も考えていますが、相手校にもアプリをインストールしてもらう必要があるので選定に悩むのと、メタバースを使うことに意味のある実践とは何かという点です。「アバターだからこそ気軽に話せる」といった心理的な安心感を評価できればと考えています。
●他校の先生との質疑応答
Q「ビデオカメラによる遠隔交流だと、何が問題だったのでしょうか?」
斉田 先生「先生の端末1台だけをZoomにつないで、大型提示装置を使って、みんなで画面を見ながら交流していたので、距離感がありました。では、みんなの端末をそれぞれつなげばいいのかと言えば、それだけだと、メタバースである必要がなくなってしまうので困っています」
●長崎大学 瀬戸崎 典夫 先生のコメント
Zoomと違ってメタバースの場合は、建築物や畑などをつくることもでき、空間的な配置が重要になってきます。また、自分の見た目に劣等感を抱き、それがコミュニケーションの弊害になっている子であれば、自分ではない「ビジュアル(見た目)」になりきることもできますし、即興で声が出せない子であれば、自分の考えを事前にテキストに起こした上で、ボイスとして流すことも可能で、そういう子どもたちの支援という切り口もあり得るのではないでしょうか。
●山梨大学 三井 一希 先生のコメント
私の場合は、メタバース空間を教室の全員で、あえて対面でやってみたことがあります。たとえば今、自分が何をしているのかという状況を色別のバッジのようなアイコンで示すことで、可視化します。そうすることで、情報収集している人同士、整理分析している人同士が協働しやすくなります。これを同じ学年全体で行えば、教室の壁を超えて、協働相手を見つけることも可能になります。
まとめのご挨拶

生成AIを使い、問いをつくり、深い学びにつなげる
日本女子大学 名誉教授/専門委員長 吉崎 静夫 先生
来月、専門委員長は私から四天王寺大学 木原俊行先生に引き継ぎますので、今日が専門委員長としては最後の挨拶になります。今日お聞きして、生成AIの教育利用は避けられないと思いました。私は現在74歳ですが、鞭打って、最新の研究に取り組んでいます。
3年目の先生に授業をしていただいた後、課題を改善する手立てを考えるリフレクションをしてもらいました。その後、Google社の生成AI「Gemini」に授業の課題と手立てを聞いて、先生に再度リフレクションしてもらうと、AIのコメントが的確で、授業の内容が深まりました。これからの授業改善は、同僚の先生たちと批判し合うリアルの良さと、生成AIとの対話という、この二つを併用していくのではないかと思いました。
もう一つ、強調しておきたいのは、問いをつくるということです。先生や仲間、生成AIと対話し、リアルをデジタルで支えていく時代に入ったのだと思います。そうやって問いを深めて、また新たな問いをつくるサイクルが続いていくわけです。そして最後が、深い学びです。個々の知識がばらばらではいけなくて、関連づけて構造化し、見える化すること。これにはやはり、一人一台端末が有効です。
民俗学者は「ハレとケ」とよく言いますが、今日は、まさにハレの舞台です。日本を代表する教育工学の研究者である専門委員の先生方との交流を、このあと楽しんでください。
第3部 交流会
第2部終了後には、先生方による交流の場が設けられました。助成先の皆様や専門委員の先生方が、この日の事例を振り返りながら、情報を交換し、交流を深めました。