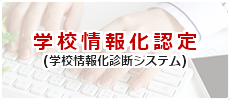財団が設立された1973年(昭和48年)。
世界に目を向けると、2月には為替市場が変動相場制に移行し、ドル/円相場は308円から一時260円台まで円高に進んだ。(その後1985年のプラザ合意まで200円台後半から前半に徐々に円高方向に推移。)
10月には第四次中東戦争が勃発し、それをきっかけに第一次石油危機(オイルショック)に見舞われ、日本国内でも「狂乱物価」と呼ばれたインフレが急激に進行し、生活必需品の買い占めなどが社会問題となった。
他方それまでの急激な経済成長の負の側面とも言える公害・環境問題への対策が喫緊の課題となるなど、戦後の高度成長期から安定成長(低成長)期への転換期であったと考えられる。
このような情勢のもと、日本の学校教育も、社会の進展と変化、あるいは教育の多様化への対応が求められるなど、下記のような大きな変節の時期を迎えていた。
- 2年前の1971年(昭和46年)には、当時の中央教育審議会(1952年設置、現在の中央教育審議会の一部にあたる)により、「今後における学校教育の総合的な拡充整備のための基本的施策について」の答申である「46答申」が為された。
- この答申は、明治初年と第2次世界大戦後に行われた教育改革に次ぐ「第三の教育改革」と位置付けられ、学校教育全般にわたる包括的な改革整備の施策を提言している。(文部科学省ホームページより)
- 近代学校制度創設100年目の節目であり、又、文部省の「視聴覚教育研修カリキュラム標準」が作成発表された年。(財団25年史より)
- この年は義務教育学校の<教材基準>に共通教材として視聴覚機器が位置づけられ、重視されてから7年目。(財団25年史より)
- 各地域での視聴覚資料の教育や教員研修の拠点となる「視聴覚センター」に対する国家補助が開始されたのも1973年(昭和48年)であり、この年を契機に各地でセンターが建設されることになった。(財団25年史より)
当財団の設立の背景には、上記のような学校教育の動向、特に視聴覚教育への関心の高まりも大きく影響していたと思われる。