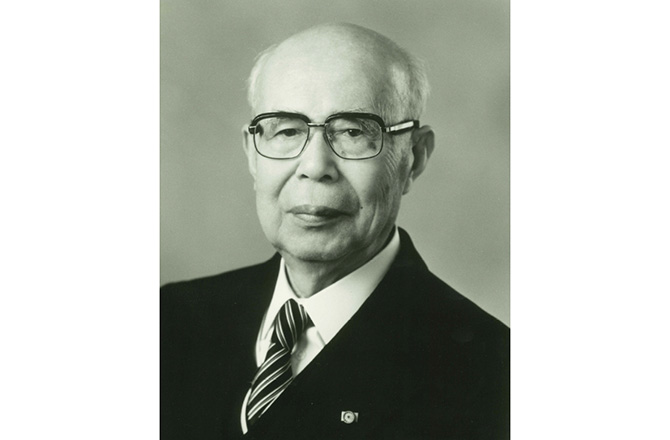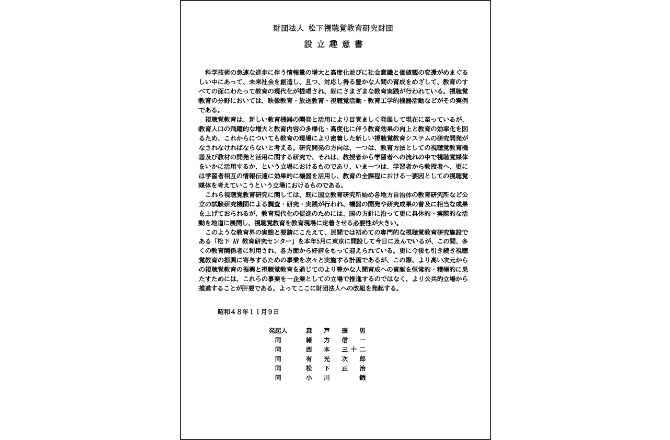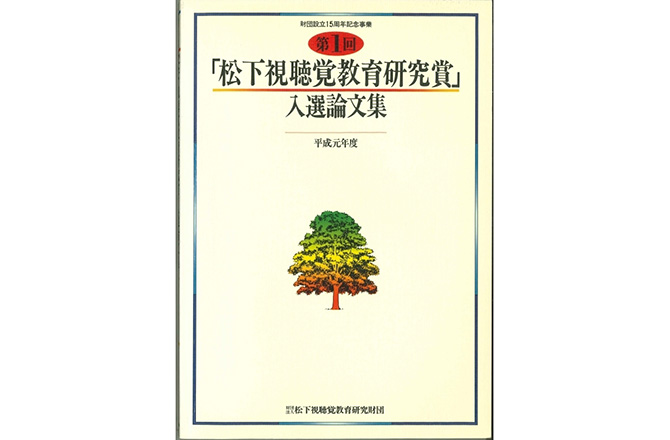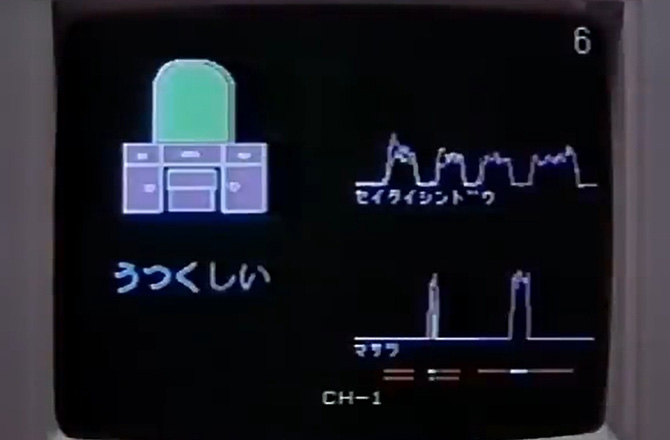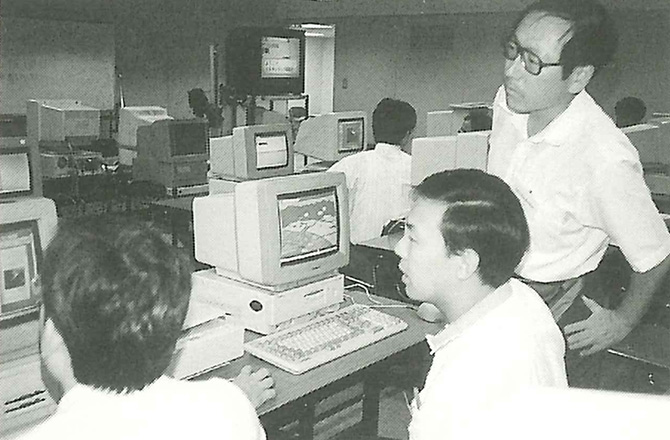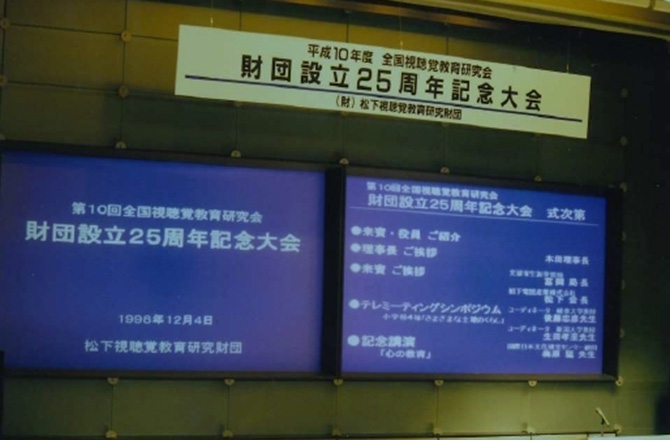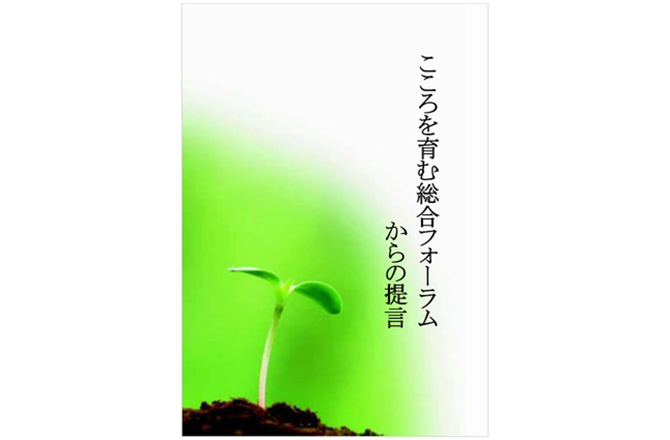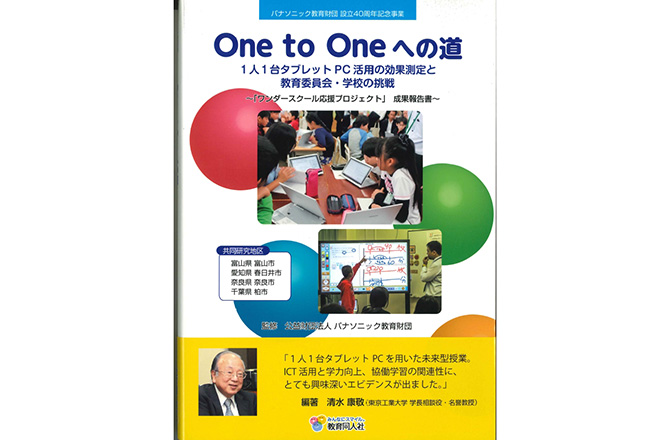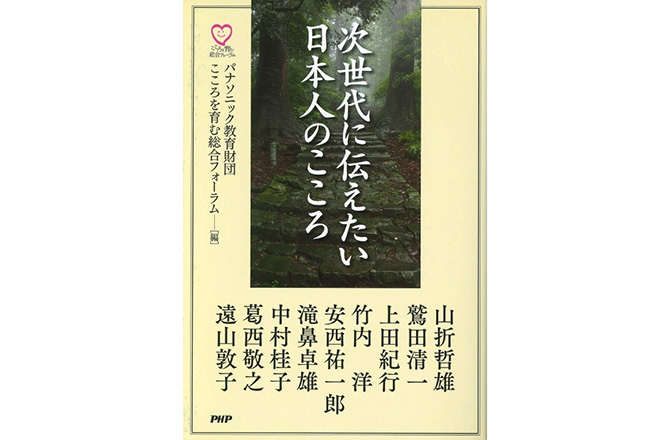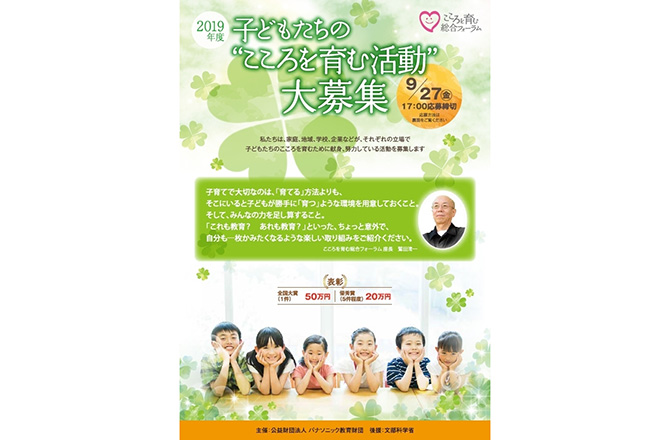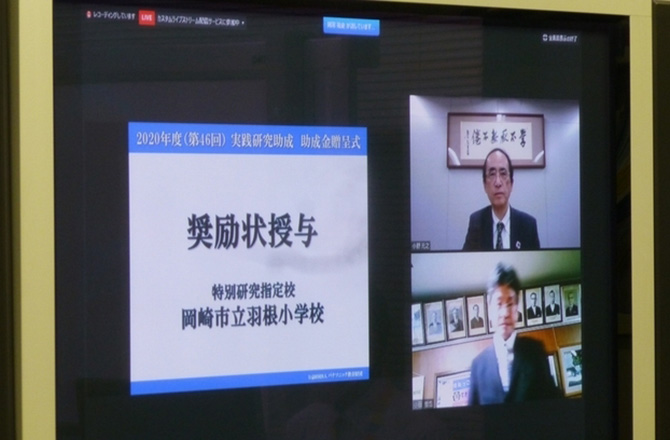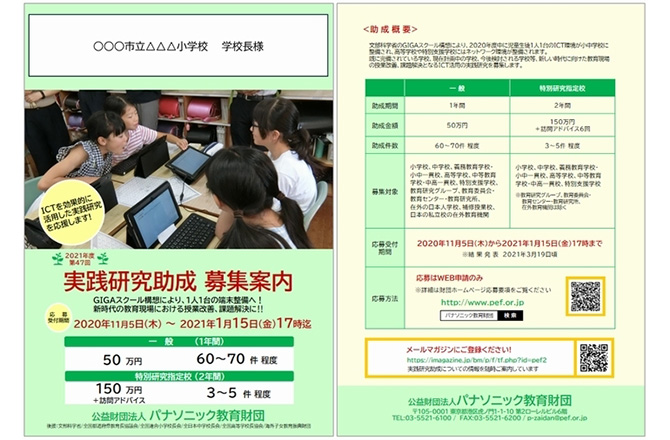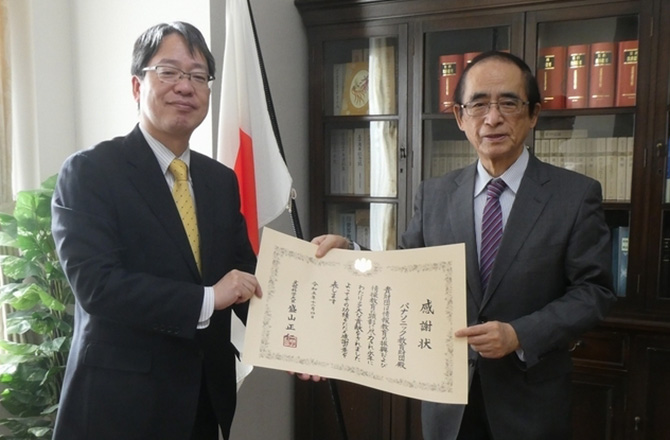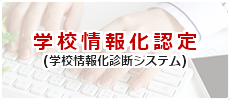1973年(昭和48年)
- 円為替変動相場制へ移行
- 第四次中東戦争~オイルショック
- 読売巨人軍が日本シリーズ9連覇
- 組織 12月に「松下視聴覚教育研究財団」設立 初代理事長 森戸辰男氏
- 研修 東京御成門の「松下AV教育研究センター」と、大阪梅田の「LLスクール大阪教室」において、暫定的な研修会実施
1974年(昭和49年)
- フィリピン ルバング島で旧日本兵発見
- プロ野球巨人の長嶋茂雄が引退
- 気象庁の「アメダス」が運用開始
- 研修 文部省の後援を受けて、教員・教育関係者向けの定期「AV研修会」がスタート
- ・東京の「松下AV教育研究センター」主に、大阪、札幌、福岡等の会場でも
- ・年間を通じて、VTR・OHP・LLの活用のための研修会を実施

1975年(昭和50年)
- 沖縄国際海洋博覧会 開催
- 「およげ!たいやきくん」大ヒット
- マイクロソフト 設立
- 助成 「視聴覚教育研究助成」がスタート
- ・対象は幼稚園・保育園、小学校、中学校、高等学校、特殊教育諸学校(*当時の標記を使用)
- ・下記の2カテゴリーで募集
「特定課題」:教育メディアの総合的な活用方法の開発、あるいは改善・充実
「自由課題」:視聴覚教材の活用について当面している課題に関するもの - ・第1回の募集に587件の応募、特定課題6件と自由課題40件、計46件が採択
- 発信 機関誌「視聴覚ニュース」創刊 当初は年数回の不定期発行

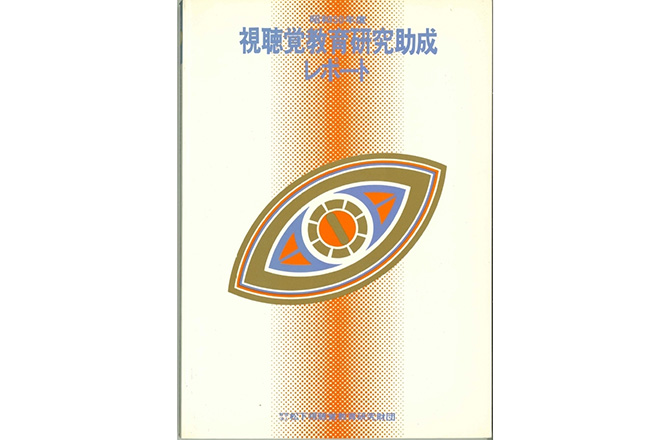
1976年(昭和51年)
- VHSビデオテープレコーダー発売
- アップルコンピュータ設立
- 発信 「視聴覚教育研究大会」がスタート
- ・第1回大会は、熊本県河内町の小学校を会場に開催
- ・大会テーマ「放送、視聴覚教材の効果的な利用のあり方を考えよう。」
- ・校種別の分科会、パネル討議、坂元昂先生の講演などが行われた
- *「視聴覚教育研究大会」は、2002年(平成14年)まで継続
- 発信 「視聴覚教育研究助成レポート」年次発刊スタート
1977年(昭和52年)
- 日本初の気象衛星「ひまわり」打ち上げ
- 白黒テレビ放送が廃止 完全カラー放送へ
- 研修 研修会受講者 延べ5000名を超える
- 発信 広島大学出版研究会より財団として初の出版物「マルチメディアと授業の構成(共著)」を出版
1978年(昭和53年)
- 新東京国際空港(現成田国際空港)開港
- 日中平和友好条約調印
- 研修 VTR活用のための研修用ビデオソフト3巻が完成 その後1982年までに全17巻を完成
1979年(昭和54年)
- 初の国公立大学共通一次学力試験実施
- 研修 英語教育の振興施策に呼応して「AV・LLスタッフ養成講座」「LL教材研究会」を新設
合わせて「LL用ビデオ教材」を完成
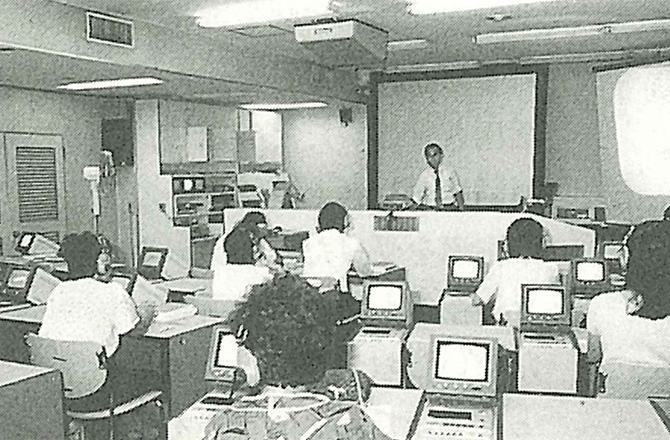
1980年(昭和55年)
- モスクワ(夏季)オリンピック開催するも日本を含む67か国が不参加
- 助成 視聴覚教育研究助成の枠組み改訂
- ・従来の「特定課題」を「指定課題」と改称し、「自由課題」との2カテゴリー制に
- ・「指定課題」では助成期間を2年とし助成金も増額、加えて財団の専門委員による中間指導を実施
1981年(昭和56年)
- スペースシャトル「コロンビア」宇宙空間への初飛行
- 研修 視聴覚教材の自作ニーズ応えるために「OHP/VTR特別コース」を新設
- 発信 「日英視聴覚セミナー」を開催
1982年(昭和57年)
- CD(コンパクトディスク)プレーヤー発売
- 研修 定期AV研修会に「パソコン研修」を組み込み、パソコン分野の取り組みを強化
- 発信 「マイコンの教育利用に関する日米シンポジウム」を開催